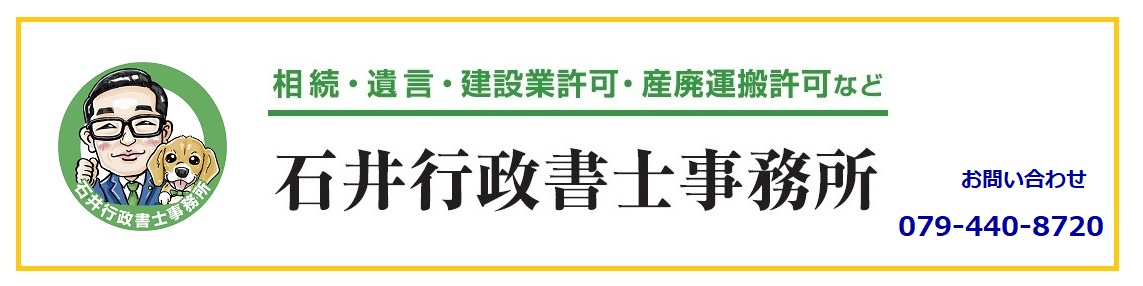新規許可申請に必要書類の例
以下は、お客様にご用意いただく書類の一例です。
※ 必要な書類の量は、各営業所の状況により異なります。お気軽にご相談下さい。
【例】 経営業務の管理責任者 個人事業主 → 確定申告書類5年分
法人の役員 → 履歴事項全部証明書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 確定申告書(5年分〜)
- 領収書や請求書、発注証明書、請書など工事の経歴がわかるもの(5年分〜)
- 資格認定証明書のコピー(資格がある場合)
- 修業(卒業)証明書のコピー(指定学科を卒業している場合)
- 経営管理者及び専任技術者の常勤性を示す書類(健康保険証写しなど)
- 財務諸表、決算書(5年分〜)
- 従業員名簿など、現在雇用している従業員がわかるもの
- 法人であれば役員全員(監査役除く)、個人であれば個人事業主等の略歴書
- 定款(法人の場合)
- 株主名簿(定款どおりである場合は不要)
- 主要取引先金融機関名がわかるもの
- 営業所の写真
- 営業所の使用権限を示す書類(賃貸契約書など)
業種の追加について
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに分けて与えられるとされています。
つまり、ある建設業の許可(例えば大工)を持っていたとしても、屋根工事について500万円以上の工事を請け負う場合は、別途屋根工事の許可を取る必要があります。
この、建設業許可申請の態様については、以下のように分けられます。
| 一般でAという業種の許可がある | 特定でAという業種の許可をとる | 般特新規 |
|---|---|---|
| 一般でBという業種の許可をとる | 業種追加 | |
| 特定でBという業種の許可をとる | 新規 | |
| 特定でAという業種の許可がある | 一般でAという業種の許可をとる | 特定廃業・般特新規 |
| 一般でBという業種の許可をとる | 新規 | |
| 特定でBという業種の許可をとる | 業種追加 |
このように、一般建設業の許可業者が一般建設業の他の許可業種を追加する場合、及び特定建設業の許可業者が特定建設業の他の許可業種を追加する場合を業種追加と呼びます。
業種追加にあたる場合、申請時の提出書類が少なくなる、申請手数料が安くなるなどのメリットがあります。
業種追加の場合の許可要件について
許可業種の追加申請をする場合でも、経営業務の管理責任者、専任の技術者、財産的基礎の要件は満たさなければなりません。
もっとも、財産的要件について、一度でも更新したことがある事業者であれば、既に届出されている決算変更届出書で「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」が確認されますので、改めて確認書類を提出する必要はありません。
ただし、一度も更新していない事業者が一般建設業の業種追加申請を行う場合は、申請時の直前の決算期の財務諸表等の提出が必要となります。
※ なお、特定建設業の業種追加の場合は、新規申請時と同様の要件となります。
許可の一本化について
制度の一本化とは
許可を受けた後、さらに他の業種を追加した場合、各許可の許可年月日および有効期間は異なることになります。そうすると、建設業者においては許可の更新時期がバラバラに来てしまうため、各許可ごとに更新手続きをするとなると、そのたびに手数料の支払いをしなければならず、また更新時期を間違ったり忘れたりしてしまいます。許可の一本化とは、それを解消するものです。
一本化の方法
許可を一本化する方法としては、以下の2通りがあります。
- 更新の際に他の許可も同時に更新する
- 業種追加の際に既存の許可を更新する
いずれの場合も、一本化される方の許可については5年を待たずして更新するため、残りの有効期間がもったいなく感じますが、更新手続き及び更新手数料が1回分で済み、次回以降の更新申請が一度で済むようになるので、メリットは大きいといえるでしょう。