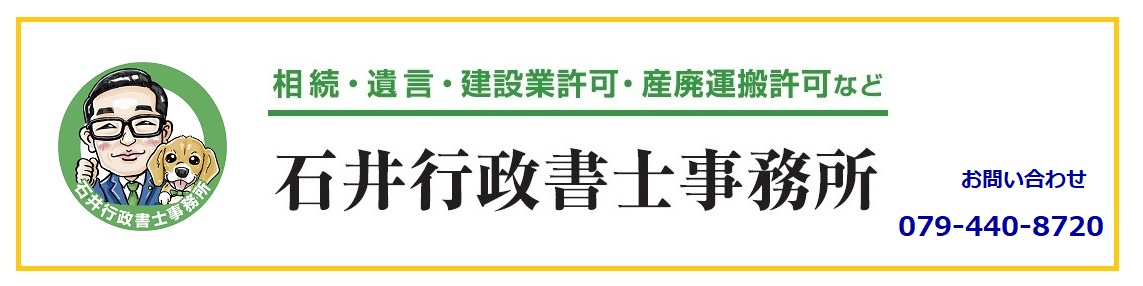遺言は、必ず必要?
もし、きちんとした形で遺言が残っていれば、遺されるご家族での余計なトラブルを避けることができます。また、有効な遺言があれば、各種相続手続の手間を省くこともできます。
当事務所では、基本的には、すべての方に、遺言作成は必要であると考えています。
遺言を作成していない場合はどうなるの?
遺言を作成していない、もしくは遺言が見つからない場合、相続人間で遺産分割協議をすることになります。もっとも、相続人全員にとって最適な分配というのは、中々決められるものではなりません。仲のいいご家族でさえ、遺産分割協議となると、話がなかなか進まないものです。
また、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないため、ご家族が疎遠な場合や、すぐに連絡がつかない場合は、一向に相続財産に手が付けられないということもありえます。
遺言を作成しておいた方がいいと思えるパターン
■子供がないおふたりさまの夫婦
遺言書を作成せず伴侶が亡くなってしまった場合は、亡くなった方の親(又は祖父母)が存命の場合は2/3、親(又は祖父母)がなく、亡くなった方の兄弟がいる時は3/4が残された伴侶の相続財産となります。自分が亡くなった時に全財産が伴侶に相続されると勘違いされている方が結構いらっしゃいます。お子様がいない夫婦はお互いに遺言書を作成しておきましょう。
■相続人がいないおひとりさまの方
独身で親や兄弟姉妹(甥姪)など相続人がいない場合は残された財産は国庫に帰属する事になります。生前お世話になった特定の方に遺贈する場合や団体に寄付する場合などは遺言書の作成が必須です。
■家業の後継者を指定したい場合(事業承継)
事業の後継者を指定し、その方に事業の基盤である土地や工場及び株式などを譲渡したい場合。
■ほとんどの相続財産が住んでいる土地、建物のみの場合
相続財産のほとんどが自宅などのように簡単に分けられない場合はトラブルになり易いです。 子供がいない夫婦であれば、兄弟姉妹と自宅を売却して分割するケースや息子や娘が複数の場合も自宅を売却して分割などとなるケースは多くみられます。裁判所で行われる遺産分割調停の約3/4が相続財産5000万以下の場合です。
■二世帯住宅に住んでいる方
息子夫婦や娘夫婦と二世代住宅に住んでいる場合で子供が複数いる場合、他の兄弟から法定相続分を主張され、自宅を売却して財産分割せざる得ない状況になる事も少なくありません。
■内縁関係の方
婚姻届けを出していない内縁関係の場合は相手が亡くなってしまった場合は相続人ではありませんので遺産を相続する事はできません。伴侶に財産を残す為には必ず遺言書の作成が必須です。
■先妻の子や後妻の子がいる等親族関係が複雑な方
再婚をしており、先妻にも後妻に子供がいるが、法定相続分と異なる相続をしたい場合。
■認知していない子を認知したい場合
遺言によって認知をする事ができ、法定相続人となります。認知した子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の1/2となりますので、相続分以上に相続させたい場合も遺言で指定できます。
■相続人以外の特定の方に遺贈したい場合
面倒をみてくれた息子の嫁、甥や姪又はお世話になった知人など法定相続人以外に方に財産を遺贈したい場合。
■財産を相続させたくない相続人がいる場合
暴力を振るなど素行の悪い息子や離婚訴訟中の配偶者、事実上絶縁状況の養子など、相続人ではあるが自分の財産を相続させたくない場合。
■行方不明の相続人がいる場合
行方不明の相続人を除外して他の相続人のみでなされた遺産分割協議は無効です。相続財産を分けたり、不動産を登記する事もできません。 遺産分割協議をする為には不在者の財産管理人の選任や失跡宣告(失跡してから7年)の申立てなど手続きや時間が掛かります。
自筆証書遺言の作成サポート
民法では、自筆証書遺言の書き方について、厳格な要件を要求し、この要件を満たせていない遺言を無効としています。
せっかく書いた遺言が無効にならないように、注意が必要です。
当事務所では、自筆証書遺言の作成サポートとして、遺言原案の作成と財産目録の作成を承っております。
【自筆証書遺言の5つの作成要件】
| 全文自書 | Wordやワープロで作成された遺言は無効です。鉛筆で作成しても要件を満たしますが、消えてしまう可能性もありますし、なるべく避けるべきです。 ← 法改正あり。 |
|---|---|
| 日付の自書 | 遺言は複数ある場合、一番新しいものが効力ある遺言とされます。また遺言作成時に作成者が遺言を作成する能力があったのかを判定しますので日付の自書が要求されているのです。年月のみで日付のない場合、または○年○月吉日などは無効です。 |
| 氏名の自書 |
遺言の作成者を明確にし、遺言作成者本人の真意を証明するためです。 |
| 押印 | 実印でも認印でもかまいませんが、遺言者の意思を明確にするために、実印が望ましいでしょう。 |
| 加除訂正の方法 | 加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民法968条2項)。つまり訂正印を押し、欄外に訂正の内容や加えた文字、削除した文字等を記載して行います。なお、この方式にのっとっていない訂正等は無効になりますが遺言までは無効にはなりません。 |
(例1)『自宅は長男○○に相続させる』…自宅という記載が不明確です。どの不動産を相続させるかまでの特定が必要です。
(例2)『(住所で)兵庫県高砂市○○町〇番〇号の土地を長女△△へ相続させる』…住所での記載は不明確です。土地は地番で、建物は家屋番号で記載しましょう。
(例3)『■■銀行の定期預金は長男と長女で分けなさい』…どういった割合での分けるかの記載までするべきです。