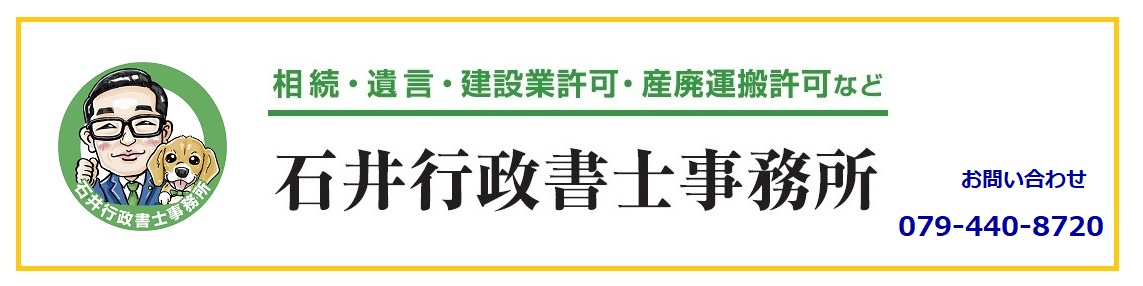風俗営業とは
風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)において規定されている、以下のいずれかに該当する営業をいいます。
- キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業を除く。) ← 低照度飲食店
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの ← 区画席飲食店
- まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業を除く。) ← ゲームセンター
許可の要件
風俗営業許可を取得するためには、3つの要件があります。
①人的要件
申請者及び管理者が次のいずれかに該当する場合は許可を受けることが出来ません(風営法4条1項)。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消されたものが法人である場合その時の役員も含む)
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由に該当しないこと)
- 法人でその役員のうち上記の欠格事由に該当する者があるもの
※上記に書いたこと以外にも欠格事由になる場合があります。
②構造的要件
営業所の構造又は設備が、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないときは、不許可となります(風営法4条2項1号)。
- 一定以上の客室面積を確保すること。
- 営業所の外部から客室が見えないこと。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと。
- 客室の出入口に施錠設備がないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く。)。
- 一定の照度を確保すること。
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以上とならないように維持すること。など…
1号の営業の場合、客室の床面積は和風9.5㎡以上、和風以外16.5㎡以上。
4,5号の営業を除く。
3号の営業を除く。
1,2号の営業 5ルクス以下とならないように維持する。
3,4,5号の営業 10 ルクス以下とならないよう維持する。
③場所的要件
営業しようとする場所が「用途地域」であるか、一定の範囲内に「保護対象施設」がある場合は、不許可となります。
※用途地域とは、都市計画法で定める地区の定義で、建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールのことをいいます。
兵庫県の用途地域による制限
| 第1種低層住居専用地域 | 営業禁止地域 |
|---|---|
| 第2種低層住居専用地域 | |
| 第1種中高層住居専用地域 | |
| 第2種中高層住居専用地域 | |
| 田園住居地域 | |
| 第1種住居地域 |
営業禁止地域 |
| 第2種住居地域 | |
| 準住居地域 |
※ 風俗営業許可は、都市計画法上の用途が住居系の地域では許可されません。
保護対象施設による制限
| 施設 | 地域 | ||
|---|---|---|---|
| 第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | |
| 学校、図書館、保育所又は認定こども園 | 70m | 50m | 30m |
| 病院又は診療所 | 50m | 30m | ――― |
※ 距離は、施設敷地の境界からの水平面直線距離をいう。
※ 保護対象施設から上記の距離を置かなければ、風俗営業許可を得ることはできません。